【例文あり】ただの書類ではない!「学修計画書」の基本的な書き方
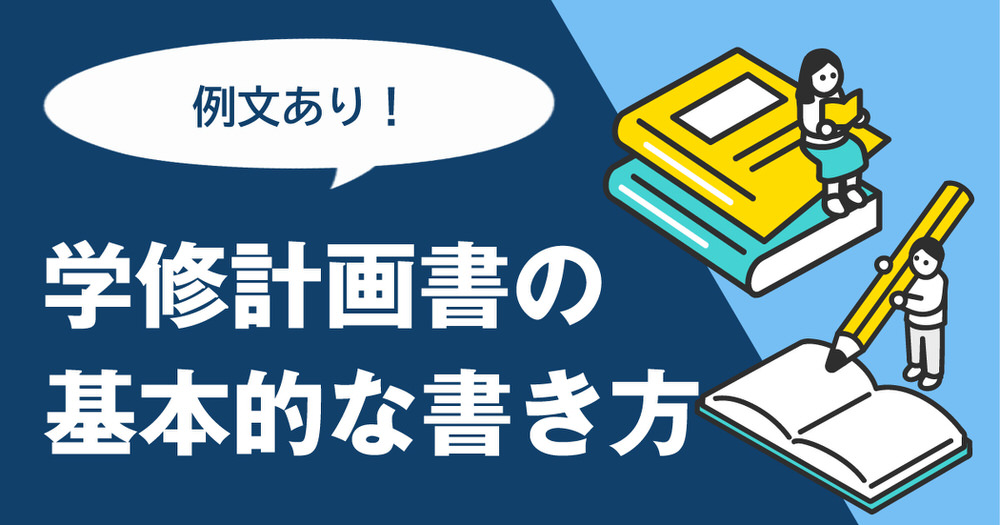
人生で一度は留学してみたい、と思う人もいるのではないでしょうか?
語学留学では不要ですが、大学への留学には語学スコアの取得やビザの用意など、多くの手続きが必要になります。
その中でも、多くの人がつまずいてしまうステップの一つが「学修計画書」です。
留学を志す方であれば、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
この「学修計画書」は、言うなれば「学びの設計図」です。
自身の学びたいことを明確にし、言語化することで、志望大学への合格可能性が高まるだけではなく、奨学金獲得のチャンスが広がったり、帰国後の活動も変わります。
この記事では、学生時代に留学を経験した筆者が、学修計画書の正体やその重要性、書き方や構成のコツまで「実際に使用した学修計画書」を例にアドバイスします。
学修計画書とは何か?
学修計画書って何?
「学修計画書」とは、留学先で何をどう学ぶか明確に示す計画書です。
留学した大学で、
- どのようなテーマや分野を専攻して学ぶか
- その理由や背景
- 履修計画や将来の目標
などを、論理的かつ具体的にまとめることが求められます。
どんな時に使うの?
海外大学への出願時はもちろん、在籍する日本国内の大学における交換留学プログラムへの応募や、奨学金の申請などの場面でも提出を求められます。
大学や国によっては提出が義務づけられているところもあり、その重要度が非常に高い書類です。
なぜ必要なの?
審査官は「なぜこの大学を選んで、何を学ぶのか」を知りたがっています。
「絶対にここで勉強したいです!!」といった熱意も非常に大切ですが、それだけでは相手は説得できません。
適切なリサーチをもとに、綿密な計画性と目的意識を伝えることが必要です。
学修計画書は、あなたの「熱意」と「行動計画」の両方を言語化し、伝えるツールなのです。
他の書類との違い
学修計画書とよく比較されるのが「志望理由書」です。
両方を一つにまとめて提出することもありますが、使い分けられると安心です。
| 志望理由書(Personal Statement) | 学修計画書(Study Plan) |
| ・「なぜこの大学に行きたいか?」を説明する ・人柄や価値観にフォーカスした内容となることが多い | ・「何を学びたいか?」を説明する ・学問的な興味や、研究テーマ、履修計画などに特化 |
学修計画書の重要性
留学先や奨学金の合否に直結する
学修計画書は、ただの「形式的な提出物」ではありません。
あなたの留学先や、奨学金の合否を左右する大事な要素の一つです。
特に、提携大学間の交換留学プログラムなどは、国内で一定の成績を収めている場合、語学スコアさえ満たせば留学に応募できるケースが多く、その間口は意外に広いです。
似たような学力や経歴を持つ学生が、同じ大学や奨学金制度に応募することもある中で、「本当にこの大学で学びたいか?」「明確な目的意識はあるのか?」といった視点で判断される学修計画書は非常に大切になってきます。
自身の理解を深める機会にもなる
学修計画書の重要性は、大学や奨学金の選考のみにとどまりません。
実は、留学を志す学生本人にとっても「自分の軸」を見出す貴重な時間になります。
冒頭にもあったように、「海外にいきたい!」「この大学で勉強したい!」といった熱意だけでは留学することはできません。
あなたの海外生活をいろいろな面で支えてくれる存在がいる以上、その人たちを納得させるだけの「論理的な説明」が必要になります。
実際に留学を経験した筆者も、学修計画書の作成に取りかかるまでは、留学への希望が漠然とあるような状態でした。
奨学金の選考に応募する過程で学修計画書に出会い、はじめてその思いを分解して言語化するようになったのです。
その作業を通して、留学への熱意が非常に論理的にイメージできるようになっただけでなく、自身が潜在的に抱いていた新たな側面に出会うこともできました。
帰国後に就職活動をした際も、当時の活動から学んだことを生かすことができました。
書き方と構成のコツ
学修計画書の正体と、その重要性についてまとめてきました。
ここでは、学修計画書の基本構成について「Why」「What」「How」「Future」の4つの観点からまとめます。
留学の目的(Why)
まず、そもそもなぜ留学したいのかまとめましょう。
- 日本ではなく、なぜ海外の大学で学びたいのか?
- なぜその国/大学なのか?
を説明することが求められます。
これまでの経験をからめてまとめると、説得力がぐっと増します。
学びたいテーマ・分野(What)
次に、留学先で学びたい内容を説明しましょう。自身が興味のある分野や、その理由を伝えます。
このときも、抽象的な動機になってしまうのではなく、具体的なきっかけや問題意識を組み合わせることをおすすめします。
学生時代に限らず、授業や書籍、これまでの体験などをベースに説明しましょう。
学修計画(How)
3つ目に、留学先の学習内容をより具体的に落とし込みます。
前段の「学びたいテーマ・分野」とは違い、より現地の生活をイメージした内容にすることが大切です。
- 留学先で受けたい授業(実際の科目名で)
- 学習方法(ディスカッションやフィールドワークなど現地の大学が実施している内容)
などをまとめます。
スポーツサークルやボランティア活動、インターンなど、学外の活動に触れても良いです。
この部分で大切になるのが「リサーチ」です。
留学の目的や学びたい内容がはっきりしていても、現地の生活をイメージしづらいような学修計画になっていては意味がありません。
留学生を多く迎えている大学は、大学の基本情報から、各学部の特徴、授業の科目名などを公開しています。
インターネットや大学の国際交流室などを活用して、よりリアリティのある内容に仕上げましょう。
将来の目標(Future)
最後に、留学で経験したことや得た知識を、将来どのように活かすかまとめましょう。
卒業後のキャリアプランや、社会貢献の方法を説明します。
「留学して終わり」ではなく、その後も一貫した軸に沿って活動する意欲が伝わることで、より説得力の高い学修計画書になります。
「学修計画書」の例文
筆者が学生時代に留学をした際、奨学金の選考で実際に作成した学修計画書を紹介します。
選考では、学修計画書をベースにした書類選考の後、面接を経て、無事に奨学金の支給を勝ち取ることができました。
※大学1年生(当時)の時に書いたため、文章の拙さが散見されるかと思います。あくまでも、全体の構成や要素を参考にしていただければと思います。
| 1.志望動機、留学の目的 私が留学を志望するのは、メディアが果たす役割を海外で学び、国際的な視座でジャーナリズムを捉えたいと考えるからだ。 私は、メディアやジャーナリズムに強い関心がある。国の舵取りを担う政治などの中心的な役割がどのような働きをしても、それを取材し伝える側の一存で、世間はいかようにも変えられるからだ。 さらに、かつては「伝える側」「伝えられる側」の関係ががはっきりと区分されていたが、すべての人がどちらの役割も担えるようになっていたり、フェイクニュースの量が多くなっていたりと、「世間の出来事や話題を正しく民衆に伝える」というメディア本来の目的意識が薄れつつある。 その本来の姿を、異文化交流を通して捉えたいと感じた。 また、世間の出来事を十分に知ることのできない地域に住む人々が、情報を取得し、さらなる国際協調へとつなげるための糸口も探りたい。 2.志望大学における学修計画 私が志望する大学では、ジャーナリズムやメディア関係の他にも、国際社会やジェンダー、グローバリゼーションなど、社会学における幅広い分野の授業を履修することができる。異なる文化や価値観の中で過ごす人々とともに、メディアやジャーナリズムと関連づけながら学ぶことで自らの教養を深めたい。 具体的には、第一希望の大学では、「Media」「Journalism」「International Politics」「Gender」「Culture and Society」「Global Migration」「Religion」などを履修したいと考えている。 3.将来の展望 将来的には、新聞記者として社会に貢献したいと考えている。留学を通して培った思考力や多角的な視点は、記者としての活動に不可欠な資質だ。 自身の視野と感性を広げることで、社会に信頼される記者になりたい。 |
まとめ
学修計画書は、留学を実現するための重要な要素であるとともに、あなたの人生や価値観を見つめ直すとても貴重な機会です。
今回紹介した内容はあくまでも基本的な要素で、もっとあなたらしい内容にしても良いでしょう。
自分と向き合いながら、時に誰かに頼りながら、あなた自身の言葉で学修計画書が紡がれることを祈っています。
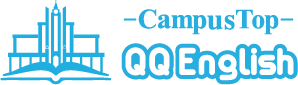
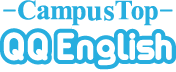


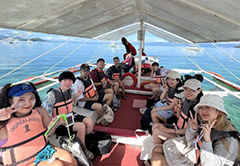










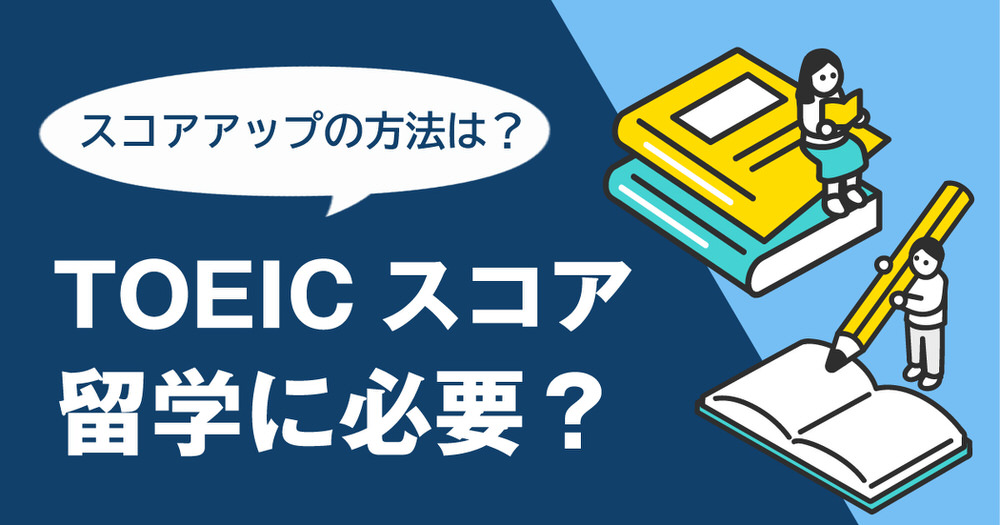




 留学品質のレッスンをオンラインで
留学品質のレッスンをオンラインで
 こども専用オンライン英会話
こども専用オンライン英会話
 英語コーチング
英語コーチング